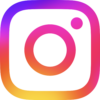第8節 ウルクへの旅路(Day2)
◆Day2
翌朝、ウトゥーとエンキドゥの一行は、日の出とともに朝食を済ませ、ロバ車に乗ってウルクへ向かった。
「ウルクにはあなたみたいな人がたくさんいるの?」
「そうですね、人はたくさんいます。私みたいな、というのは、どういったイメージでしょう?」
「えーっと…」
「ふむ」
「えっと、親切な人!かな?」
「…ありがたく受け取っておきます。それでは、親切な人として、到着までウルクの生活のことをまたひとつふたつ、お伝えさせていただきましょうか」
やった!と小さく声を上げ、エンキドゥは、ウトゥーのするウルクの話に耳を傾けた。何だかよくわからないながらも、わくわくして、「楽しい気持ち」を感じていた。
昼過ぎ頃になると、遠くで白い煙が立つのが見えた。
近づくとそこは川べりで、川の近くの大きな木の近くにテントが張られていた。テントの近くに立つ人影がふとロバ車の方に気付き、「お待ちしておりました!エンキドゥさま!」と、元気よく挨拶をしてきた。
ウトゥーのように従者を引き連れた偉丈夫は、さわやかな笑顔を浮かべて、彼らの元に歩み寄った。この青年が、神殿男娼から派遣された二の矢である。
「ここからエンキドゥ様をウルクにご案内するのは、私カーシです。」
どうぞお見知りおきを、と馬車の扉越しに今度は深く腰を折る礼をする。
「しばしお持ちを」
「うん?」
ウトゥーは、車を降りカーシとなにやら立ち話を始めた。ぽつんと残されたエンキドゥは不安な面持ちで二人を見つめる。声は潜められていて、耳のいい彼女でも聞き取ることはできなかった。
少しの後ウトゥーが戻り、残念そうに微笑みながらこう告げた。
「私はこれから所用があり、一緒にお供できません。ここからはあの、カーシがご案内します。ご安心ください。私と同郷のものです。これまでの事情も、しかとお伝えしておきました。ご不便はおかけしませぬでしょう」
口調は申し訳なさそうではあったが、てきぱきとエンキドゥの荷物を降ろしながら話す。降りようとしないエンキドゥにも、さぁ、と手をのばすのだが、まだ状況が呑み込めていない。
「短い旅でしたが、とても楽しかったですよ。またウルクでお会いしましょう」
「…」
「失礼いたします」
ヒョイとエンキドゥを抱え、ゆっくりと地面におろす。
「また、ウルクで会えるんだよね?」
「ええ」
変わらず優しく答えるウトゥーの表情が、どこか悲しげにも見えたが、人を疑うことをまだ覚えぬエンキドゥは、もやりとしたものを抱えながらも、わかった、と小さくうなずいた。それを見届けるとウトゥーはすっと踵を返し、振り返らぬようにして入れ替わるようにロバ車に乗り込んだ。
ウトゥーを見送った後、しんみりした空気を吹き飛ばすように、カーシは改めてエンキドゥに名乗ってから、朗らかに話しかける。
「少しお疲れになったでしょう!ささ、こちらにお座りください」
丸太のいすに腰掛けさせると、彼は従者をと共に、テーブルの上に豪勢な料理を運びこんだ。芳醇な香りの小麦とラム肉のシチュー。クサープというパン、レンズ豆はほろほろに煮られていて食欲をそそる。麦酒を、それからシカールという酒精が供され、それらは所狭しと羅べられた。そのどれもが綺麗な器に盛りつけられていて、初めて見る光景にエンキドゥはごくりと唾を飲んだまま、驚きテーブルの料理をただただ眺めていた。
「エンキドゥさま、さあ、お召し上がりください」
「えっと…」
「ああ、ウルクでは、野菜や肉を調理したものをスプーンで口に運び食べるのです。飲み物は器に注ぎ、器から飲むのです。それが人間の習わしなのです」
エンキドゥは、促されるままにスプーンを持った。それから、腹の虫が鳴いていたのを思い出して、いつものようにがつ!と皿の上の食べ物をかきこんだ。
元気で何よりだ、というふうににこにことその姿を眺めながら、カーシは傍らでに侍り、エンキドゥのスプーンの持ち方を整え、食べ物を口にしたまま喋らないこと、大きく開いた足は閉じるように、テーブルに肘は着かないようにするなど、一つ一つのマナーを丁寧に手取り足取り優しく指導した。
シカールの酔いが回ったのか、エンキドゥは、顔がほてり、何だか愉快な気持ちになった。少し口うるさくも感じるぐらいのカーシのマナー講座ではあったが、優しく諭されるためそれに嫌な気持ちになることはなく、それになんとなく、今学んだことには既視感があるようにも思えた。
「わたし、」
と、何事か口を開きかけたところで、ふらりとめまいが襲った。
「おっと、お酒を7杯も飲んでいますから。不慣れだったのですね、失礼いたしました」
「ううん、いいよ~・・」
エンキドゥは心が満たされ幸せな気持ちになった。
「少し休みますか?失礼しますよ」
と、カーシは椅子にぐにゃりと溶けているエンキドゥを抱きかかえ、天幕の中のベッドにそっと寝かせた。
「いいにおいがするね、」
「ええ、特製の香りなんだ」
ベッドの傍の香炉には複雑な彫り物がされていたが、エンキドゥはそちらを見ることはなく、すよ、とまどろみの中に落ちた。カーシは、エンキドゥの着ているレースのあしらわれたシャツのボタンに指をかけた。
「手間のかかる着物を選んでるねぇ。いい趣味だ」
この服を彼女に与えたウトゥーはここにはいない。仲間であるが、同時に客は奪ったもの勝ちの世界でもある。俺の趣味には合わないな、と誹りながらひとつ、美しいお嬢さんだ、とあやしながらまたひとつ、そのボタンをはずしていく。
添い寝の手遊びのように、カーシにしてみれば無駄に多いボタンを外し切り、ゆっくりエンキドゥの唇にキスをしようと顔を近づける。手のひらをする…と若い肌に沿わせ、
「うえええええっ…」
エンキドゥがおもむろに起き上がり、ベッドから転がり落ちてそのまま這うように天幕の外に出た。目を白黒させて突然の展開にらしくもなくカーシはベッドの上で固まった。ベッドの上で固まるなんて、いつ以来だ。
「おえー--っ!!!!」
耳をふさぎたくなるような、げぼげぼいう音が響く。
記念すべき、エンキドゥ初めての二日酔いである。
はぁ・・・・・と、長すぎるため息をついてから、カーシは自分もまた二日酔いになったかのようにしばし頭を抱えたが、まだおえおえ言っている少女を放っていくほど外道にはなれなかった。
「大丈夫かよ…」
もはや口調を取り繕うこともせず、天幕の外に様子を見に行き、ちんまり丸まったエンキドゥの背中を大きな手のひらでさする。幸か不幸か、前が開きっぱなしになってた服は濁流の被害を受けなかったようで、もはや兄か父の心持ちになってしまったカーシはエンキドゥの服を汚れる前に引っぺがし、天幕にあった毛布で適当に体をくるみ、気持ち悪い…とうめく体をできる限り揺らさないように天幕の中に戻した。
「お水をお持ちします。今夜はゆっくりお休みください」
「あ、ありが…おえぇ…」
「黙って寝ていてくださいね」
「ふぇん…」
その後、おえおえしたりう~う~したりしている毛布の塊に水を与え、寝かしつけるまでゆっくりさすってやった。ようやく落ち着いたのか再び寝落ちたのを確認し、カーシは再び大きなため息をこぼした。
「俺としたことが…」
酒精を利用しようとして、逆に見事に失敗してしまっている現状が、もはやおかしくなってきてしまって、ひととき任務を忘れたかのように、カーシはそのままごろりとエンキドゥの横に転がり、自分もまた眠りに落ちた。雲の少ない夜で、天幕の外には星が綺麗だ。