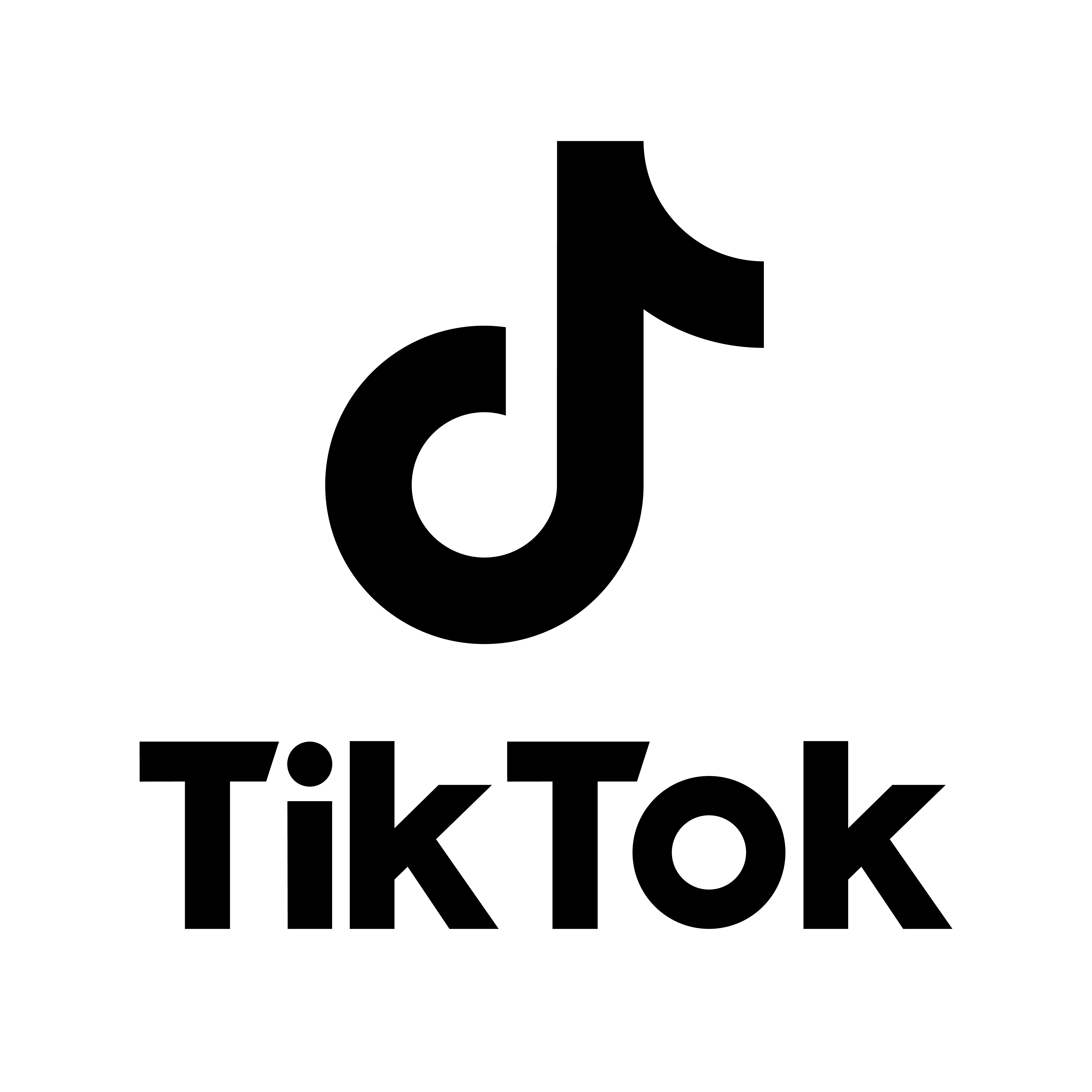世界の頸椎牽引装置の構造比較とストレッチルーネの革新
はじめに
頸椎(首)の牽引装置は、古代から現代にかけて世界各地で開発され、様々な原理で首の負担軽減や矯正に用いられてきました。代表的な装置には、古代ギリシャのヒポクラテスのベンチ(Scamnum)、17世紀のグリソンの輪(Glissonのループ)、20世紀の頭蓋骨トング(Crutchfield/Gardner-Wellsトング)、ハローベスト(Halo traction)などがあります。本報告では、これら既存装置の構造と作用原理を比較し、各装置が「テコの原理(支点・力点・作用点)」を用いているかを検証します。そのうえで、日本発の頸椎ストレッチ器具「ストレッチルーネ(StretchLoona)」が頭(力点)・首(作用点)・ルーネ(支点)を一体化したテコ構造を世界で初めて採用した牽引装置であるかどうかを評価します。 各デバイスの構造的特徴を明確に比較するため、本文では主要装置の原理と構造上の支点・力点・作用点の有無を整理し、最後に比較表を提示します。
歴史的な頸椎牽引装置とその原理
古代:ヒポクラテス式牽引ベンチ
古代ギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前5世紀頃)は、ヒポクラテスのベンチと呼ばれる装置で骨折や脊椎の変形治療に牽引の概念を導入しました。患者の身体を長い木製台に固定し、ロープと滑車、ウィンドラス(巻き上げ器)によって骨や関節に持続的な牽引力(張力)を加える構造です。この装置自体は大きな木製フレームであり、支点=ベンチ固定部、力点=ロープによる引張力、作用点=骨・関節という形で外力を加えていました。ヒポクラテスのベンチは「現代の牽引テーブルの前身」とされ、テコというより軸方向の直線牽引に分類されます。顎を支点にするような構造ではなく、患者の体と装置に外力をかけるシンプルな機械でした。そのため顎や頭部をテコ構造の一部とする要素はありません。
17~19世紀:グリソンの輪と吊り下げ牽引法
頸椎牽引が医学に再登場したのは17世紀です。英国の解剖学者フランシス・グリソン(Francis Glisson, 1597–1677)は1650年頃、「グリソンの輪(またはループ)」と呼ばれる顎と後頭部にかける吊り帯を発明しました。これは患者の顎の下と後頭部を布製ハーネスで支え、上方に引っ張ることで首を伸ばす牽引具です。当初は小児のくる病や脊柱側弯症の治療に用いられ、頭部に紐をかけてぶら下がるシンプルな構造でした。グリソンの牽引は支点=特定の固定点を持たず、頭部全体を下顎と後頭部から包んで上方へ引く方法で、テコの三点構成(支点・力点・作用点)を明示的に設計したものではありません。その後19世紀に至るまで、首吊り帯(ヘルターベルトとも)による牽引法が整形外科や神経科で補助療法として用いられました。例えば1880年代には神経梅毒の歩行障害治療に全身懸垂法が導入され、同時に首の牽引も試みられています。しかし、これらはいずれも頭や顎を単に牽引ベルトで吊り下げる方式であり、頭部の重さを利用したテコ作用ではありません。
20世紀前半:頭蓋骨トングと直線牽引の発展
頭蓋骨トング(Skull Tongs)とは、頭蓋骨にピン(鋭いボルト)を刺して骨ごと牽引する器具です。代表的なクランチフィールド・トング(Crutchfield tongs)はアメリカのW.G.クランチフィールドが1933年に報告したもので、鋭い2本のピンを左右の頭蓋骨側面に食い込ませて固定し、それを滑車と重りで引っ張る仕組みでした。実際にはクランチフィールド以前にカナダのH.H.ヘプバーンが1920年代に氷用トングをヒントに同様の頭蓋牽引具を考案し、ゴムチューブでバネ張力をかける工夫も行っていました。頭蓋骨トングでは支点=頭蓋骨に刺さったピンの先端(頭蓋骨との摩擦で支える点)、力点=下方向にぶら下げた重り、作用点=首(頸椎)となります。しかし、ここでの「支点」は人体ではなく金属ピンそのものであり、頭蓋骨は牽引される対象です。顎や頭部を装置の構造要素として活用しているわけではなく、身体とは独立した器具(ピンと重り)で直線的な引張力を加える設計です。重力による牽引力を使う点では原始的なテコ(滑車)といえますが、顎を支点とするテコの原理は採用していません。頭蓋骨トングは主に頸椎骨折や脱臼の整復に用いられ、非常に強力な牽引が可能ですが、ピン孔からの感染や神経損傷などリスクも伴いました。
なお、1929年には病院で簡便に使える頸椎ハルター(Halter device)と呼ばれる装置が登場しています。これは下顎と後頭部に当てる布製の吊り具を頭に装着し、天井の滑車を通した重りで首を引く装置です。言わばグリソンの輪の近代版で、現在でもドア枠に吊す家庭用牽引キットとして広く知られています。構造はグリソンと同じく下顎と後頭部を支持し、そのまま上方へ牽引するもので、テコ構造ではありません。むしろ牽引ロープと重りが一直線上に作用する純粋な直線牽引です。この種のハルター牽引は簡易ながら顎への圧迫痛や頭部後方へのずれが問題となり、短時間しか継続できない欠点が指摘されてきました。実際、中国の医学者は「従来の頸椎牽引装置の多くは環状の枕ベルトで下顎縁を引き上げる方式(いわゆる“ヘルメット型”)だが、これは顎先に痛みを与え、数分で患者が苦痛を訴える」と報告しています。このように20世紀前半までの装置は、いずれも外部の重りや力を利用した直線牽引が中心で、人体の一部(顎や頭)をテコの支点・力点に組み込む発想は見られません。
20世紀後半:ハロー牽引とモダンな頸椎牽引器具
ハロー装置(Halo traction)は、頭部に金属製のリング(ハロー)をボルトで固定し、それを支点に頭と胴体を繋ぐことで頸椎を安定させたり牽引したりする装置です。1950年代末、米国の整形外科医ジャクリーン・ペリーとヴァーノン・ニッケルが開発し、「The Halo: A Spinal Skeletal Traction Fixation Device」という論文で発表しました。ハローベストでは頭蓋骨に計4~6本のスクリューを前額部と後頭部にねじ込み、金属リングを頭に固定します。そのリングをベスト(胴着)や滑車システムと連結し、頭と体幹を相対的に引き離すことで頸椎を伸展・固定します。ハロー牽引にはHalo gravity traction(ハロー重力牽引)と呼ばれる応用もあり、脊柱側弯の小児患者の頭にハローを付けて上方から吊り下げ、患者自身の体重を利用して徐々に脊柱を伸ばす方法も行われます。ハロー装置の場合、支点=頭蓋に刺入した各ピンの先端(リングを介して頭部を支える点)、力点=吊り上げる力(重りや体重など)、作用点=頸椎と考えることができます。しかし、リングとピンが一体化して頭部と固定されているため、装置内での可動のテコ機構は存在せず、基本的には固定した頭部を軸に体を引き伸ばすものです。つまり頭や顎そのものが機械的なレバーとして動くわけではありません。ハロー牽引は強力かつ有効ですが大掛かりであり、患者は長期間入院下で過ごす必要があります。日常生活で手軽に使えるものではないため、より簡易な装置への需要も生まれました。
1980年代以降、病院や在宅向けに簡便な頸椎牽引器具が多数開発されています。例えば空気圧式の頸椎カラー(エアネック牽引具)や、ねじ機構で高さを変えられる調整式頸椎カラーがあります。米国特許にも1990年代に「携帯型・膨張式の頸椎牽引デバイス」が複数出願されており、例として頸椎カラーで頭蓋骨を持ち上げる装置(US6050965, 2000年)や、空気注入式の頸部トラクション装置(US5950628, 1999年)が挙げられます。典型的な構造は、肩に乗せる環状のカラー(土台)と、下顎・後頭部を支える上部ブレースからなります。ユーザーはこのカラーを首に巻き、ねじや空気圧で上下の間隔を広げると、カラーが肩を押し下げつつ顎・後頭部を押し上げて首を伸ばします。このような装置では、支点=カラーとブレースの接合部(機械ヒンジなど)、力点=スクリューの回転力または空気圧、作用点=顎と後頭部を介して頸椎となります。一見テコのようですが、構造的には「上下から首を挟んで広げる」直線動作であり、顎を回転支点にして頭の重さを利用する発想ではありません。むしろ外力で頭蓋骨を持ち上げる点で、従来型の牽引と連続性があります。実際、中国の近年の特許公報でも「現有の頸椎牽引装置は大掛かりで柔軟性に欠け、操作が不便で牽引効果と体験性が良くない」と指摘されており、改良案として下顎支持板と後頸部支持板を肩台に可動連結し、ねじ機構で下顎板を上下させる牽引具(2020年, CN111773032A)が開示されています。しかしこの装置も、支点と力点は装置内のヒンジとねじであり、頭そのものを重りにはしていません。以上のように、21世紀初頭までに存在した頸椎牽引器具は大小様々な形態がありますが、どれも外部から加える力による牽引であって、顎や頭部を装置構造の一部(レバーの一要素)として積極的に利用した例は確認できません。
ストレッチルーネの構造と他装置との比較
ストレッチルーネの発明とテコ原理の応用
こうした中で、2000年代に入って開発されたのが日本の「ストレッチルーネ®」です。発明者の元屋敷英樹氏が自身の肩こり経験から発案し、2006年に日本で特許出願・取得、続いて米国・中国でも特許を取得した革新的デバイスです。ストレッチルーネは一見シンプルなフィットネス用具ですが、顎を載せる窪み付きの本体と、そこに頭をもたせかけて軽く前傾するという利用方法によって、「テコの原理」を頸椎ストレッチに応用した世界初の装置といえます。具体的には、支点=顎(本体の顎当てに固定される点)、力点=頭部の重さ(前方に倒れる頭の重量)、作用点=頸部(首筋に生じる上向き牽引力)という三点構成を意図的に設計しています。ユーザーが椅子に腰掛けてストレッチルーネ本体のくぼみに顎を載せ、上半身をわずかに前に倒すと、頭が前方へ落ちようとする力が顎で受け止められます。このとき頭の重みがテコの力点として働き、顎を支点に首が持ち上がる方向の牽引力が発生します。言わば人間の頭部と顎を一体化させた一本のテコが出来上がり、外部の重りや複雑な装置なしに自然な牽引が行われます。重力とテコを組み合わせた独自構造により、首への余計な負担を抑えつつ心地よいストレッチが可能になっています。
ストレッチルーネの構造上特筆すべき点は、装置の一部として人体(顎と頭)を組み込んでいることです。他の装置が「人体 対 装置」で外力を加えるのに対し、ストレッチルーネは「人体 の一部が 装置の機構として機能する」点で構造発想が根本的に異なります。顎受けに荷重がかかることで本体がテコの支点となり、頭の重量という生体由来の力点を利用して首を伸ばす作用点を得る仕組みは、調査した限り既存の文献・器具カタログには類を見ないものです。実際、本発明は「姿勢矯正用運動用具」として各国で独自性が認められ特許登録されており、「首の牽引ストレッチ器具として各国で独自性が認められた」と明記されています。これは、従来技術に同様の構造が存在しなかったことを示唆しています。
他の装置との構造的差異のまとめ
以上を踏まえ、主要な頸椎牽引装置についてストレッチルーネとの構造の違いを整理します。以下の表では、各装置ごとに原理(テコ構造の有無)、牽引力の発生源、身体との接点を比較しています。
※表中の「テコ構造ではない」は、装置内に回転支点を設けて力の方向や大きさを変換する仕組みがないことを示します。ストレッチルーネのみが、人間の顎を支点とした第一種てこ(支点が中央にあり、一端に力点、反対側に作用点があるてこ)に該当するユニークな構造となっています。
結論:ストレッチルーネは世界初の「顎を支点とする頸椎牽引デバイス」
調査した範囲では、ストレッチルーネ以前の頸椎牽引装置において「頭(力点)・首(作用点)・ルーネ(支点)が一体となってテコの原理を形成する構造」は確認できませんでした。古代のヒポクラテスのベンチから近代のハロー装置・各種牽引カラーに至るまで、従来技術は外部から首を引っ張る直線的な牽引が基本であり、支点・力点・作用点の三点を人体の一部と装置で構成するという発想は見られません。その意味で、ストレッチルーネの構造は従来の延長線上にはない構造的イノベーションといえます。その独自性は日本・米国・中国の特許で保護されており、顎を支点に頭部重量を牽引力へ変換するデザインは世界的にも新規な発明として認められています。医学文献や特許情報を見ても、ストレッチルーネ以前に顎をてこの支点として明示的に利用した頸椎牽引器具の存在は示されていませんでした。このことから、ストレッチルーネは「頭(力点)・首(作用点)・ルーネ(支点)一体のテコ構造」による頸椎牽引装置として世界初のものであると結論づけられます。
最後に付言すれば、その革新的構造によりストレッチルーネは日常生活でのセルフケアを容易にしつつ、安全に首のストレッチを行える点で注目されています。従来のような大掛かりな機器や重りを必要とせず、重力とテコを活用したシンプルな設計であるため、患者の負担軽減と安全性向上にも寄与しています。以上の調査結果からも、ストレッチルーネの構造は他に例を見ない独創的なものであり、「世界初」と評して差し支えないでしょう。
参考文献(抜粋)
Hippocrates bench – Wikipedia
ResearchGate: Hippocratic bench (figure and description)
StatPearls: Cervical Traction – History and introduction
Parney IF et al. “Howard H. Hepburn and the development of skull tongs for cervical spine traction.” Neurosurgery. 2000 Dec;47(6):1430-3
Wikipedia: Halo-gravity traction – History of halo device
米国特許 第6050965号 “Cervical collar for lifting the skull of a wearer”(2000年)
中国特許 公開CN111773032A “颈椎牵引装置” 背景技術
マルゲンライフ株式会社 ストレッチルーネ 特許技術紹介サイト
マルゲンライフ株式会社 「ルーネエクササイズ&ストレッチのテコの原理とその効果」 (顎=支点・頭=力点・首=作用点の説明)
特許技術で実現するルーネエクササイズの効果
Hippocratic bench – Wikipedia
Hippocratic bench or scamnum: The Hippocratic bench is perhaps… | Download Scientific Diagram
History
Cervical Traction – StatPearls – NCBI Bookshelf
The history of modern spinal traction with particular reference to neural disorders | Spinal Cord
Howard H. Hepburn and the development of skull tongs for cervical spine traction – PubMed
CN104083238B – Jaw type traction apparatus for cervical vertebrae – Google Patents
Halo-gravity traction device – Wikipedia
Cervical spine brace and traction device – Ohana Medical Concepts, LLC
CN111773032A – cervical traction device – Google Patents
ストレッチルーネ:革新的な頸椎けん引技術とそのグローバルな展望 – マルゲンライフ – ストレッチルーネの特許技術紹介サイト
ルーネエクササイズ&ストレッチのテコの原理とその効果
| 装置名(時代) | 牽引の方式・原理 | 支点・力点・作用点の構造 | 身体部位の利用 |
| ヒポクラテスのベンチ<br>(古代ギリシャ) | 木製ベンチに体を固定し、ロープと滑車で軸方向に骨格を牽引。外力による直線牽引装置の祖型。 | テコ構造ではない(支点=固定具合、力点=ロープの張力、作用点=骨・関節)。患者の体は受動的に牽引される。 | 身体は牽引対象。顎を含め身体部位をてこ要素に利用しない。 |
| グリソンの輪(ループ)<br>(17世紀) | 下顎と後頭部に布製ハーネスをかけ上方へ牽引。吊り帯牽引による頸椎伸展。 | テコ構造ではない(支点=特定せず頭全体、力点=吊り上げる力〈重り〉、作用点=首への引張)。一直線上に力を伝達する方式。 | 顎・後頭を支点というより牽引の当て所として利用(身体は受動的)。てこ的な回転運動はなし。 |
| 頭蓋骨トング<br>(1920–30年代) | 頭蓋骨にピンを刺し重量で引く骨格牽引。Crutchfield型など。 | 器具自体ははさみ形のレバーだが用途は直線牽引(支点=ピン留め部、力点=下垂する重り、作用点=頸椎軸方向の力)。テコというより重力+滑車の原理。 | 頭蓋骨を直接固定し牽引する。顎や頭部は装置の一部ではなく、牽引される対象。 |
| ハロー牽引(Halo)<br>(1950–60年代) | 頭部リングをスクリュー固定し、体幹との間で牽引・固定。外骨骼的な固定牽引。 | 支点=頭部に固定したハローリング(装置-頭の結合部)、力点=重量やフレームの引張力、作用点=頸椎軸方向の力。レバーの回転運動はなく、固定フレームによる直線的牽引。 | 頭にリングをボルト留めするが、頭部は装置と一体化して固定される。顎は通常利用しない(顎はフリー)。身体(体重)はHalo重力牽引で重り代わりになるが、てこの支点ではない。 |
| 頸椎牽引カラー<br>(1990年代) | 肩当て+顎当てをねじや空気圧で拡張し首を挟み上げる。能動的スプリング牽引。 | テコ構造ではない(支点=カラーのヒンジ部など、力点=機械的な昇降力、作用点=顎・後頭部から首への押し上げ力)。上下に引き離す直線動作。 | 顎・後頭を当接し支えるが、装置内でテコ運動はしない。身体部位は単なる受け皿(押される点)として使用。 |
| ストレッチルーネ<br>(2006年特許) | 顎を載せ前傾することで、頭の重さを利用したてこ牽引を発生。外部動力・重り不要の自重ストレッチ。 | 支点=本体に載せた顎(顎と装置が接する点)、力点=前方へ傾く頭部重量(重力による力)、作用点=頸椎を上方へ引く力。頭が下がろうとする力を顎支点でモーメントに変換し首を伸ばす(明確な三点構成)。 | 顎と頭を装置構造の一部として活用。人体の重さ(頭部)がそのまま牽引の原動力となり、顎が機械的支点を担う。他に類例のない人体一体型のテコ構造。 |