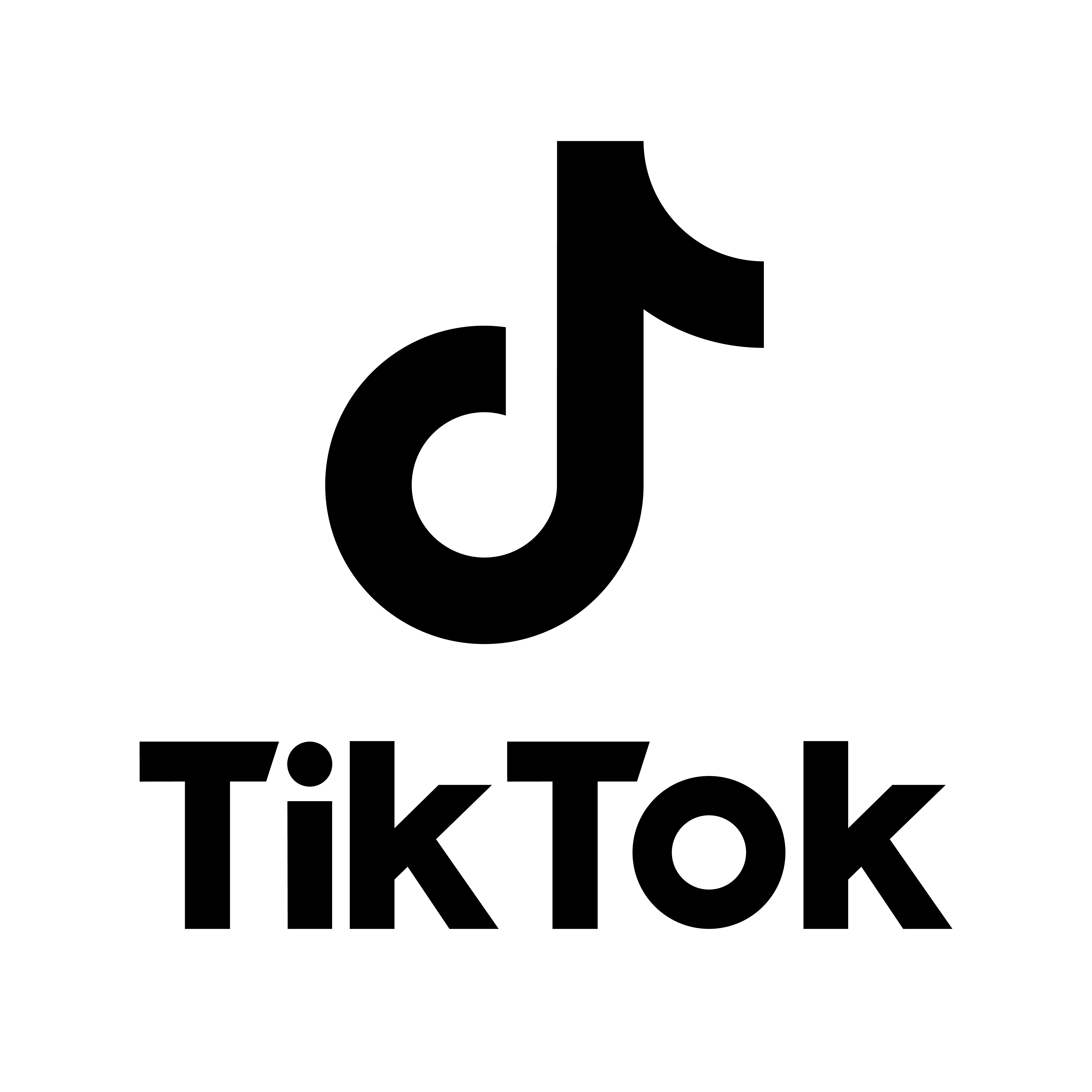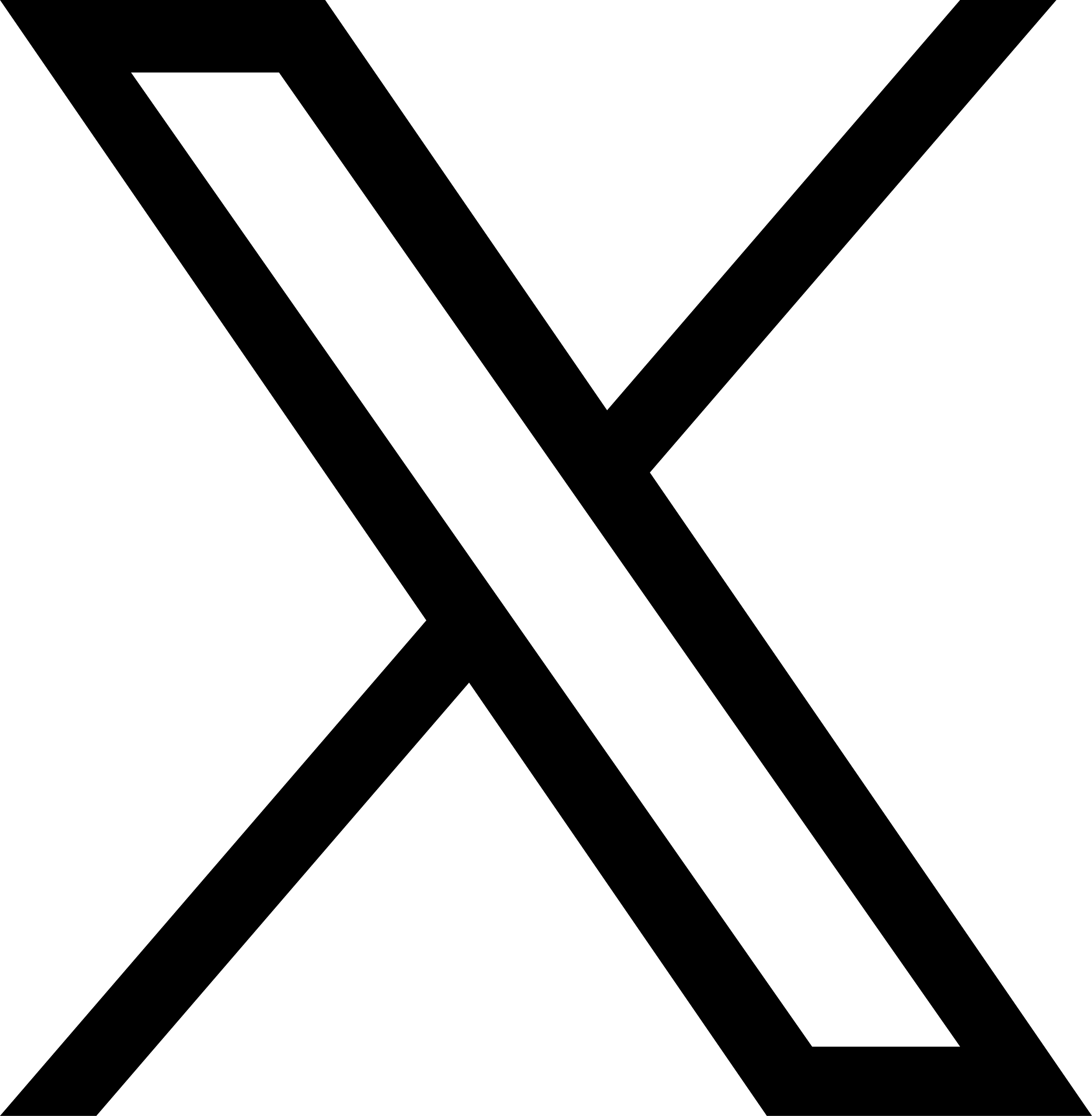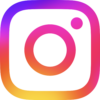第2節 大地の女神アルルの憂鬱
さて、この「大地の女神アルル」は、人間を創造した女神であり、出産の女神でもある。
ヒトの形をしながらも月夜に伸びる影のようにその上背は高く、水の滴るつららのように細長い指先は鋭利なようで存外器用に動く。
その指が懐をさぐり、するりと薄い粘土板を取り出した。
ぼわ、と淡いベールがかかったように光るそれを見ながら、アルルは極めて人間らしくため息をついた。
異国のヒジャブで口元(おそらくそこに口がある、はずだ)までおおわれているその顔は見えなかったが、きっと物憂げな表情が隠れているのだとわかる。
さきほど、彼女を呼び出したのは天空の神であるアヌだ。創造神であり、最高神である存在でもあるアヌの命はこうだ。
『ウルクの王、ギルガメッシュの横暴を何とか諫めよ』
しばしの沈黙ののち、アルルは口を開いた。
「恐れ多くも申し上げます。具体的に何をなすべきか、分かりかねます」
「ギルガメッシュの傍若無人な振る舞いを抑制するのだ。このままではウルクの民が暴動が起こしかねない」
と、アヌはたっぷりとしたあごひげを持て余すように撫でつけながらさらにそう命じた。
「アルル、お前に出来ることをすればよい」
「お言葉を返すようですが、アヌ。私がウルクの王を説得することはできないでしょう」
「何故だ」
「私の立場に、その権威がございません」
はき、と言い切るその声に、アヌは一瞬うろたえるように目を泳がせ、それからまた一つあごひげを撫でつけた。
アルルはそこに重ねるように、続けた。
「『最高神アヌ』が直接、彼の者に罰を与えれば良いのではないでしょうか?」
すい、と長い指先をそろえ、手のひらで促すようにアヌを指し、それからゆっくりと腰を折った。アヌのあごひげが。自らの指でいくらか絡まり始めた。
「…おまえも知っていることだが、彼の王は特殊な出自が、ある」
「ええ」
存じております、と腰を折ったままアルルは答える。
「父はウルクの王・ルガルバンダ、母は女神リマト・ニンスン」
「そうだ。神自身がウルクの王を選び、結ばれ、そこに子をなした。そしてその子を王とした。その事実はそれ自体が神の信託なのだ。そのギルガメッシュ王を同じ神が裁くということは、…つまり、ウルクの統治体制に問題が生じる恐れがある」
アルルはこれには相槌を打たなかった。
「神と人間の両方の魂を身に宿す半神半人のギルガメッシュは、私だけでなく、神エンリル、エンキから知恵を授け、ウルク王として信託されている。
その信託のもとにウルクを統治している。
それを罰するということは、【アヌンナキの神々】の権威を否定することになりかねない、つまり、威信に傷が付くことになる…。だから、つまり、…都合が悪い」
アルルはさすがにここで笑いをこらえきれず、目を三日月の形にゆがめ、それをおさめてから、ゆっくりと顔を上げた。
「それでは、ギルガメッシュ王の母、女神リマトから言い聞かせては?産みの母の言葉であれば、暴君とていくらか耳を貸すでしょう」
朗々とそう伝えながらも、アルルはおおよそこの後のアヌの答えが予想できていた。話が『落ち着く』ところがどこなのか、もうこの聡い神には十分見えてしまっていた。アヌはそれをわかっているのかいないのか、うむむ、と唇をしばしゆがめてから、言葉をつづけた。
「女神リマトにはすでに相談をしておる。尋ねた、…のだが、彼女の我が子への溺愛ぶりというのは、それはもう…、相談には聞く耳を持たず、逆に自慢話を聞かされる始末でな…。母の力を頼って何とか出来る状況では…」
分かりました、と、神アヌの話が終わる前に、アルルはあえて不満げな声を作り、低く答えた。多少の意趣返しである。
「それではアヌ。私は人間創造の神、『ギルガメッシュの力を凌ぐ力を持った人間』の創造をお許ししていただけますか?」
アヌは眉を寄せ、それから両眼を強く開いた。
「…なるほど。」
指先でからまったアヌのあごひげが、ゆっくりとほどけた。
「認めよう」
アルルもまた、先ほど作った不満の顔をすっとベールの中に隠し、一つ首肯した。
「アルルよ、ウルクに平和がもたらされるように、暴虐の王と競い戦える勇敢な戦士を創造せよ。さすれば彼の王の横暴を抑えることができよう」
あたかもそれが自分で弾き出した解であるかのように、アヌは鷹揚に今度こそ正しく、アルルに命をくだした。
それと同時にアヌの手の内には一枚の粘土板が現れ、その表面を指先で数度なぞった。
ぼや、と発光した盤面は沼底の宝石のような緑に色を変え、そこに文字を走らせた。
最後にぼわりとその筆跡の上を炎が走り、しっかりと焼きこまれのは、狂戦士を呼び起こす詠唱呪文だ。
アヌが粘土板を持った手をすっとかざせば、それはふわりと空中に浮かびあがり、アルルの伸ばした指先に吸い込まれるように収まった。
「かしこまりました」
と、最後にもう一度深く腰を折ったアルルは、長い指先で一度自らの顔を覆うように撫でる。
そこに奇怪な土づくりの面が浮かんだと思った瞬間には、アルルはアヌの前から姿を消した。
そうして冒頭の、ウルクの街を見下ろしての独り言へと至るのだ。
「雑、ねぇ…」
自らの神域へと戻ったアルルは、粘土板に映し出された古の魔術書を凝視しつつ、これからの術式に思いをはせた。
この粘土板にはあらゆるアヌンナキの魔法技術や歴史などがすべて詰まっている。
ただ、引き出せるのは「自分次第」だ。何が適切で、何が必要で、何が「正確」か。樹海のように張り巡らされた情報の中にどぷりと落ちぬように気を付けながら、アルルはひとつずつ、盤上に駒を並べる。
ここに召喚のための術式は刻まれているが「何」を呼ぶかは、私に委ねられているのだ。
「ウルクの王といえど、半神半人。誤って殺してしまうようなことになれば、神々からの恨みを買うだろう」
「かといって、競い戦わせ、一時その身を伏せさせたたところで…、あの暴君の悪行が一時的に収まるだけでは意味がない…」
「そもそもギルガメッシュ王、自身が変わらなければ…」
「名君に、とまでは思わずとも…だが、性質など容易に変わらない。…何か…驚天動地のような…出来事が…」
まったく、とんだ責任を押し付けられたものだ、と、アルルはまた目を三日月の形に細めた。アヌ自身が神々からの責めを逃れるために、ちょうど都合の良かったのが私なのだろうと、ふつ…と腹の奥に濁りが生まれる。
しかしこのアルル、考えても仕方のないことに時間と感情を割く性質ではない。
「然るべき時に、業は然るべきものに還る。神とて…例外ではない」
さて、私が創造した人間がギルガメッシュを殺したとして…?
創造した人間を罰すればよい。
仮にギルガメッシュに殺されたとして?
ならば、ウルクの民は創造した人間に同情するだろう。
ぶつぶつ、と低いうなりのような独り言をつぶやきながら、「解」を探ること数日。
「これ、でしょうね」
『それ』を粘土板の記憶から探り出し、アルルはようやく満足したように顔を上げた。
彼女の神域に「昼夜」の区切りはない。ただ太陽のような光は、ちょうど天頂に差し掛かっていた。