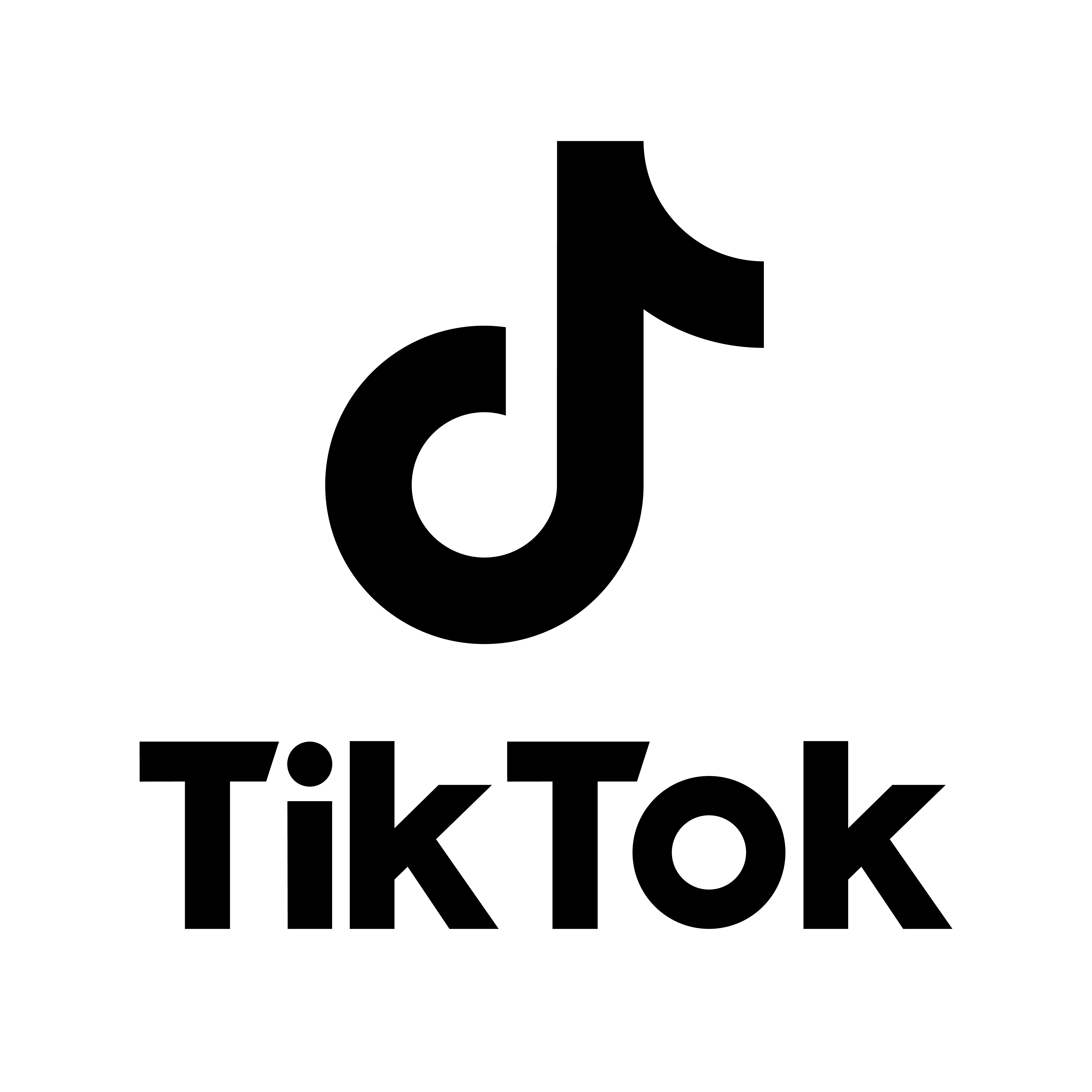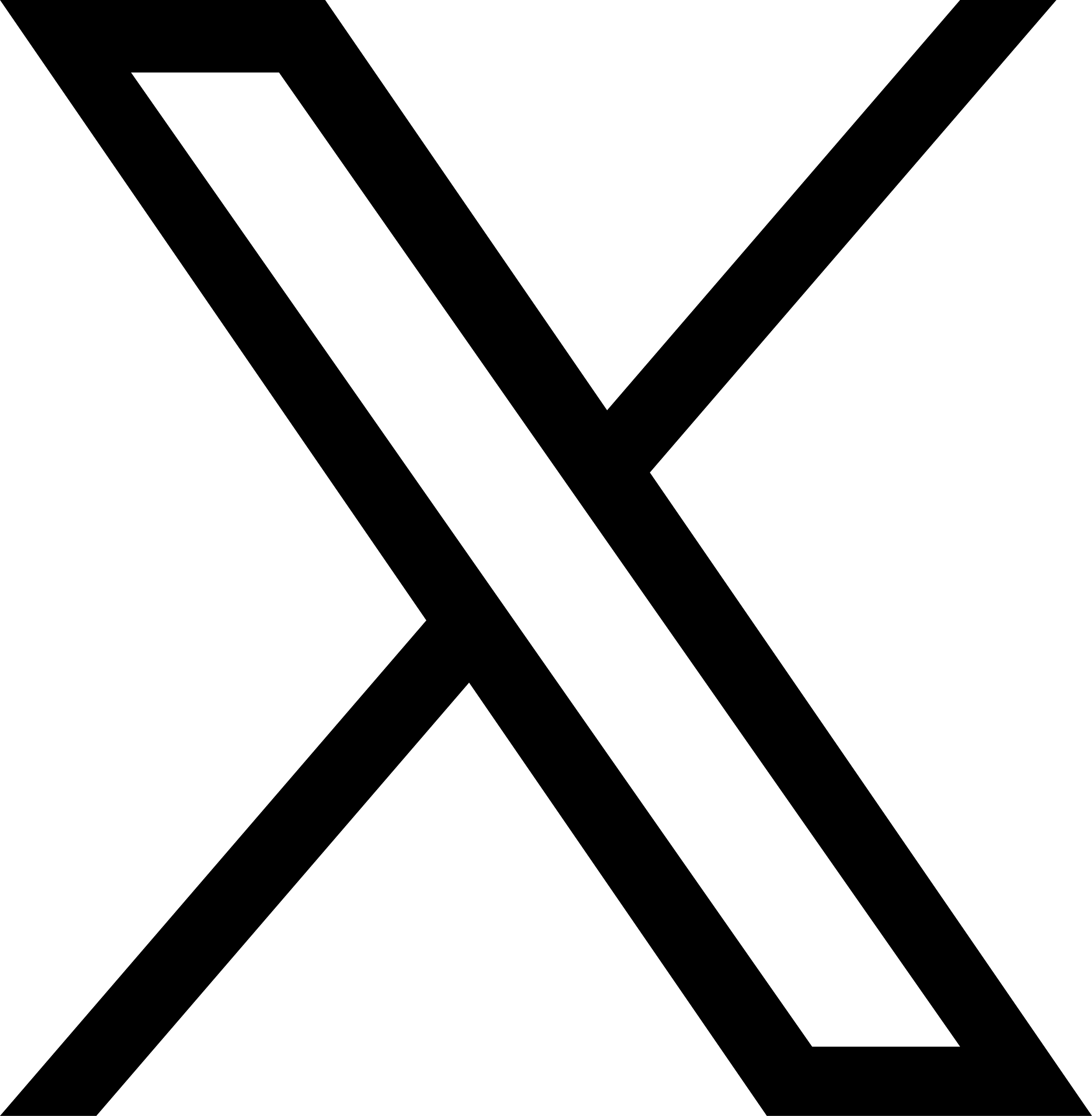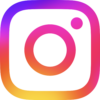第4節 杉森の番人「魔獣フワワ」前編
それから、どれくらいの時間が経過しただろうか。
葦のベッドの中で目覚めた少女は、固まった体をほぐすように大きく伸びをした。外は陽が高く昇り日差しが強いため、40度以上の高温になっていたが、堅牢な岩の洞窟内にはその熱気は入り込んでこず、人間にとって極めて快適な環境になっていた。
暗がりに目が慣れてきた少女はゆっくり周りを見回した。しかしそこには誰もいない。風が通り抜ける音だけがほんのわずか、洞窟の中に反響するばかりであった。
「エンキドゥ、」と、己に与えられた名を、無意識に唱えていた。
あのおそろしい生き物が最後にささやいた言葉。そうだ、おそろしい生き物に出会った。いや、出会った…?一瞬脳裏をかすめた朧な影の残像を追いかけようとしたが、そうすればするほど、記憶の靄が強くなっていき、少女の中に残ったのは「その影」の残響だけだった。
アルルが最後に囁いた「お前の名前はエンキドゥ」、「ギルガメッシュの…悪行を止めさせる」という言葉とアルルの影だけが記憶に残っていた。あれは何者だったのか?と考えつつ、「私はエンキドゥ、ギルガメッシュの悪行を止めさせる…」と少女は自分に言い聞かせるように声を発してみた。
少女、エンキドゥは、まずは自分がどこにいるのかを理解せねば、とベッドをおり、風の吹きこんでくる洞窟の入口へ向かった。
「・・・気持ちいい、」
洞窟の入り口に立ち、遠くを眺める。洞窟は小高い丘に位置していた。葦が生い茂る湿地と岩石の丘が点在している原野が眼下に広がっていた。見知らぬ場所ではあったが、草原から吹き上がる風を受けながら、目と耳を澄ましエンキドゥはひとりごちた。
しばらくそうして風を浴びていると、「グゥー‥」お腹が鳴った。
そこでようやく自分がひどく空腹であることに気が付いたエンキドゥは、そういえばのども乾いているな、と掠れた声で軽く咳払いをしてから、目の前に広がる湿地の、泉であろう場所にめどをつけて歩き始めた。
この世界に棲む、己を襲う敵や危険な獣などの存在など一切知らないように。
泉に至る道中、自生する木々や草木を眺めながら、無意識に食べられそうなものがないか探していた。自分にはそういった野生での生活の経験があったのだろうか?記憶は依然蘇らない。しばらくゆくと高い木になる梨のような果実をみつけ、エンキドゥはそれを取ろうと木に登る。枝の先に実る果実に手を伸ばすと、枝がしなるようになり容易に取れた。木から降りようとしたときは、足を滑らせて身長を超えるような高さから落下したてしまったが、そのときも柔らかい落ち葉が吹き溜まりに救われ、怪我らしい怪我を負わずにいた。服の隙間から転げ落ちた果実だけがいくらか傷を負っていたが、店に出すわけでもなし、問題はない。
手に取った果実や球根類、草木の葉などの臭いをかぎ、少しだけ舐め、口に含み食べられるかどうかを確かめながら歩いた。幸いにも手に取ったそれらはどれも舌をしびれさせることもなければ、人間の口に堪えられる味のものだった。親切な森だな、などと悠長に考えながらいくらかの飢えを満たしたエンキドゥであったが、彼女が通り過ぎたその道行をよくよく観察してみると、「食べられる野草類」がひときわ目立つように、本来その周りを囲んでいた草木はきれいに間引き、掻き分けられているのだが、彼女はついぞそれに気づくことはなかった。
朧に見えた長身の人影は、やれやれと肩をすくめるようなしぐさを見せて、そしてまたその姿を薄霧の中にくらませた。
そうこうしているうちに、エンキドゥは泉のほとりに辿り着いた。少し戸惑いながら、おそるおそる水を手のひらで少し掬う。冷たい。濁りもない。それを確認するや、いよいよ乾きが限界を超えたのか、おもむろに四つん這いになり、エンキドゥは獣のように水を飲んだ。
はー、と。乾きがおさまるまで息継ぎをしながら泉に顔を付けた後、ようやくエンキドゥは一息ついて空を見上げた。生き返ったような心地になり、しばしそのまま後ろに転がり地面に大の字で過ごしたが、日中のうだるような陽射しに体がほてってきてしまったので、起き上がりちゃぷ、と泉に足を浸けた。ひやりとした感覚が心地よくて、ええいと全身を泉に沈ませたエンキドゥは、水の中で仰向けになり再び天を仰いだ。水中からそのまま空へと続く青が美しかった。
そうしてしばしの休憩を取ったのち、泉のほとりの木が陰を作ってくれているところをみつけ、そこに腰かけつま先で水とたわむれながら過ごした。
そこからの数日は、そんな生活をしばらく続けた。洞窟で快適に眠り、日中は洞窟から泉までの道中で木々の果実や野草を収穫しては、泉のほとりでそれらを食する日々。あまりに穏やかで、ゆっくりと時間が流れていると錯覚するほどだった。
そんなことばかりしているうちに、そこに生きるのが自分だけではないことをエンキドゥは知った。動物たちだ。はじめはエンキドゥに警戒していたライオンや牛などの野生動物は、のんべんだらりと泉でくつろぐその姿を見て敵ではないと認識したのか、やがて近くで肩を並べて水を飲むようになっていた。そうなるとこちらも仲間意識が沸いて、狩人が作ったのであろう罠にかかった動物を助けもしたし、罠をみかければ、誰かが捕まってしまわないようにそれを打ち壊した。彼女は知らないが、それはウルクの狩人が作ったものだった。
そしてときどき道中の森で採れた木の実などをお裾分けとして分け与えれば、小さな生き物たちも肉食の動物が離れた隙をみつけてはエンキドゥのそばに寄り添った。いつしか野生の動物たちはエンキドゥを信頼し慣れ親しんでいったのだ。
そんな、穏やかな平原ライフがいつまでも続くのかなとのどかに考えていたが、えてして平穏ほど長くは続かないのは世の常である。エンキドゥは気づいていなかったが、彼女を監視しているのは「長身の影」だけではなかったのだ。
ある日、いつものように泉のほとりでくつろいでいたところに、茂みの中から、突如として2メートルは優に超える怪物が現れた。歯をむき出しにして鬼のような形相をしたその「怪物」は、ぐる、とひとつ喉を鳴らしてから、硬直しているエンキドゥを睥睨するようにしながらこう言った。
「我は杉森の番人フワワ、この土地を治めるもの」
すん、と、ひとつ鼻を鳴らす。
「貴様は何者か?」
明らかに怒りと不快を湛えたその声にあわせるように、顔に、人間の腸のような浮腫が浮き出し、皮膚の内側を暴れるように不気味に動いた。大きな歯をギシギシ鳴らし、ずし、と聞こえこそしないが重い足取りが一歩エンキドゥの元に踏み出してくる。
殺される!と、直感的に思ったエンキドゥは固まってしまった体の緊張をなんとか振りほどき、泉を離れ一目散に森に向かって走り逃げ出した。しかしその巨躯からは想像できないような敏捷さで、フワワはあっという間にエンキドゥに追いつき、後ろから羽交い絞めにする。
「ヒッ…、わ…!!」

エンキドゥの足は宙に浮き、全力で暴れたが解放されることはなかった。暴れる体の動きを収めるためだろうか、あるいは喉笛を一撃でかみちぎるつもりだったのだろうか。大きな牙のそろった口を開き、エンキドゥに嚙みついた。間一髪、暴れていたため急所は外れたが、耳や手の一部がフワワに喰いちぎられるのが分かる。
「殺される…!!」
今度こそ本格的に死を直感したエンキドゥだったが、次の瞬間、フワワがぴたりとその動きを止めた。異形の顔をエンキドゥではなく森の方に向けた。緊張の糸が切れ、恐怖の中でエンキドゥは気を失った。森にはこれまでエンキドゥが共に生活をしていた獣たちが姿を見せていた。
獣たちの鳴き声にふん、と鼻を鳴らしたフワワは、腕の中でぐたりと力を失った少女のにおいをすんすんと嗅いでから、獣たちに一声吠えて答えた。
エンキドゥが敵ではないことを訴えた獣たちは、フワワにひとつ頭を下げるようにもみえる仕草をした後、それぞれの住処に散った。