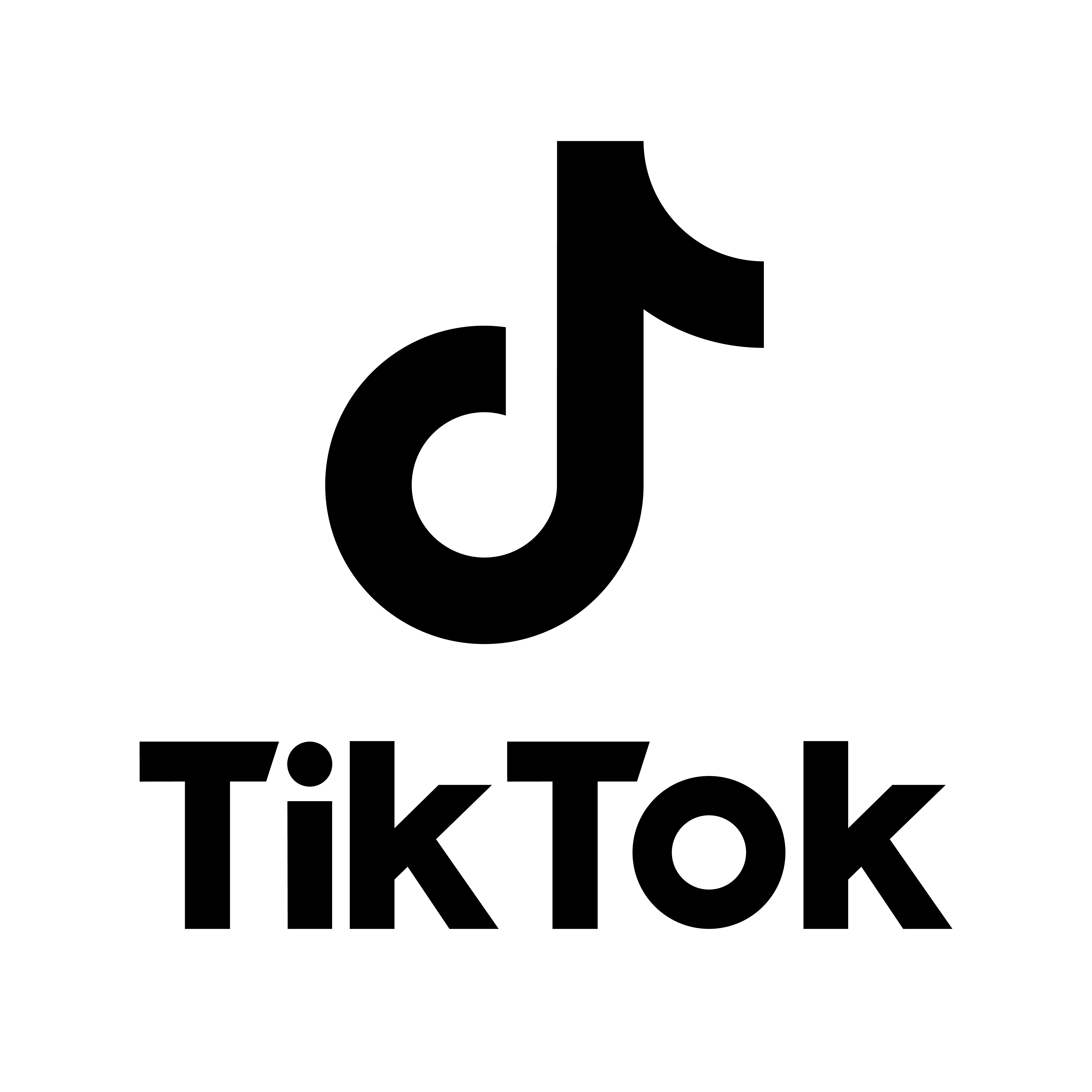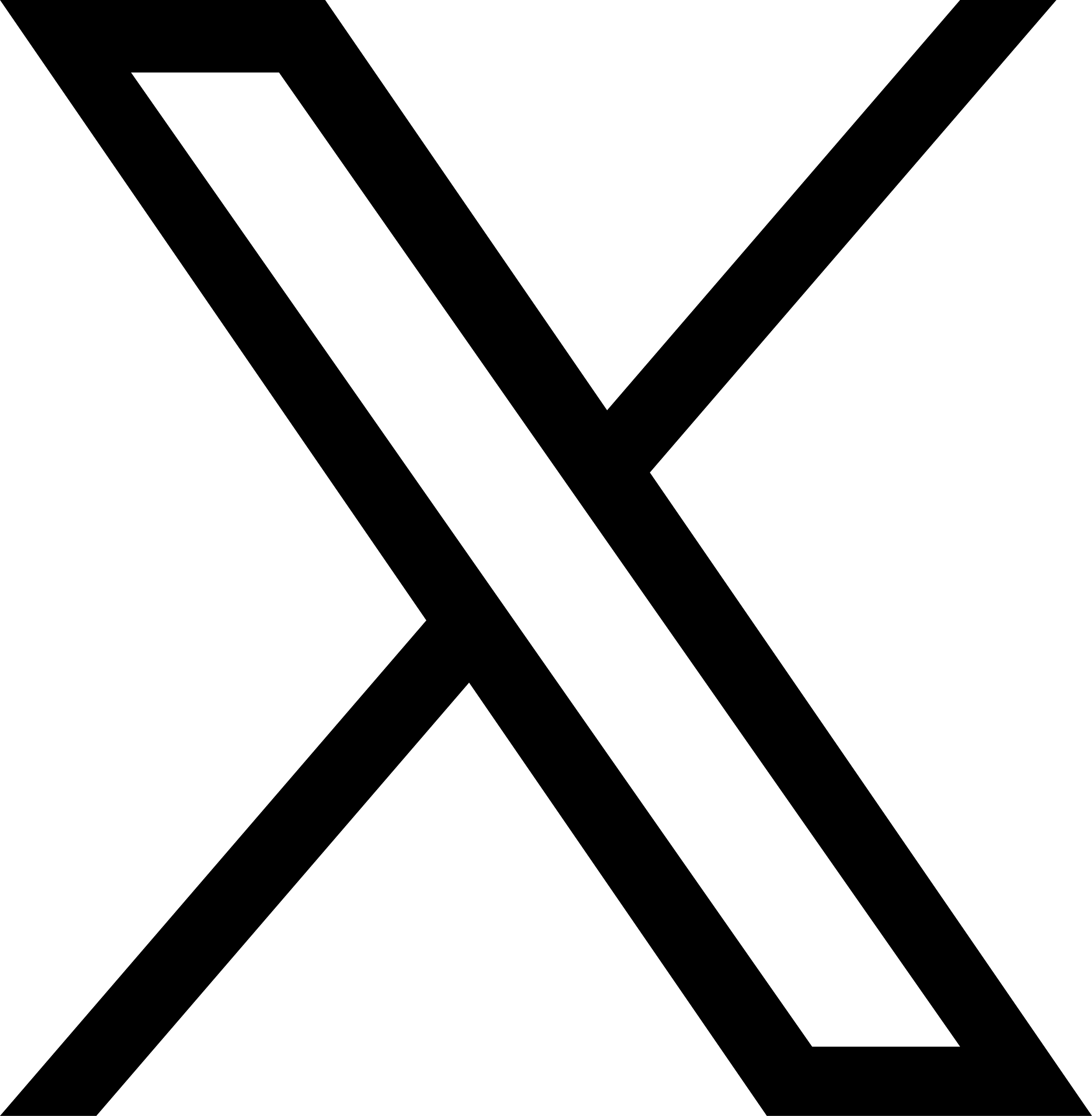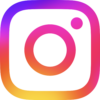第5節 杉森の番人「魔獣フワワ」後編
「ううっ」
と、体のきしむのに呻きながら、目が覚めたエンキドゥは気が付くと木陰に横たわっていた。
「よう、気が付いたか?」
「ひっ…!」
すぐ近くに座っていた杉森の番人フワワが話しかけてきたのに、エンキドゥは後ずさろうとして木の幹でしたたか頭を打った。
「はは、落ち着け、落ち着け」
先ほどは腸をむき出しにしたような異形の化け物の姿だったが、その顔は普通の人間の皮膚に嘘のように戻っており、口元も笑うように口角が上がってひょうきんな表情をエンキドゥに向けた。
「さっきは、悪かったな。お前のことを誤解していたようだ。怪我は…大丈夫のようだな」
そう言ったフワワは、ぬっと手を伸ばしてエンキドゥの頭に触れた。
「おまえ、変わった耳と手だな」
頭の上にあった猫の耳の片方はちぎれ、腕の皮は一部が剝ぎ取られている。なぜか痛みはない。エンキドゥも手をそっと頭に持っていき片方の耳がなくなっていることを理解した。それからもう片方の猫耳に触れてみたところ、耳がずるりと剥がれ落ちて地面に転がった。
「えっ…?!」
獣の毛の生えた猫の手の皮膚は喰いちぎられているが、その内側には人間の手があった。
「痛く、ない…」
はがれたところを引っ張ると、そのまま猫の毛が生えていた部分を脱ぎ捨てることができた。長手袋のよう形状のそれが、これまで皮膚と一体化しているように密着していたのだということを、このときエンキドゥははじめて知った。柔らかいシリコンゴムのように伸びる手袋の、その反対側も剥ぎ取るように脱いだ。
自分の姿は泉に映るから知っているつもりだった。でも、あの耳も…獣の腕も…まがいもの?そういえば、まさかのそこでようやく気付いたが、自分の顔の横には人間の耳がついている。そちらはどうやら引っ張ってもはずれそうにはなかった。
「私は、エンキドゥ…」
それしか知らぬ少女は、覚醒したその日ぶりにそうつぶやいた。
「おまえはどこから来た?」
「…分からない。気が付けば近くの洞窟にいて…。あなたは、どうして杉森の番人をしているの?」
「気が付いた時には、杉森の番人をしていた」
気が付いた時には、という己と同じ出自の知れなさに、なんだか少しだけ気が楽になって、エンキドゥはふふっと小さく笑った。
「神エンリルからの命令でな」
「神、エンリル?」
すぐに警戒を解くのは軽率かとは思ったが、初対面のときの憤怒の表情とは程遠い気のいい顔つきに、ここにきてから誰とも「ことば」で会話をしていなかった無意識の乾きが癒えていくのを感じたエンキドゥは、じり、と腰をずらしてフワワに少し近づいた。
フワワも、ちらりとその琥珀色の瞳をエンキドゥに向け、それからゆっくりと語った。
「実は俺も良くは知らないのだ。この杉の森に入れるのは神エンリルの許可があるものだけだ。それ以外のものは殺す。…それが私の役目だ」
殺す、という言葉が、今度はなんとも実体のない現実味のない言葉としてエンキドゥの耳を通り抜け、少女はふんふんと相槌を打った。
「だが、お前は…。なんだ、一応、もとは猫のようだしな。聞けば、森の動物を人間の罠から助けてくれたらしい。それならば俺たちの敵ではない。許されないのは『ヒト』だけだ。『動物』を殺す、許されざる『ヒト』を、俺は殺す。だが、そうだな…おまえは、杉森を守る共同体の一員だ!」
「じゃあ、今日から私たちはお友達だね!」
と、自分の生死が今まさに目の前の番人によってジャッジされたのだということをあまりわかっていないのか、エンキドゥは満面の笑みを浮かべてそう言った。
「ああ、よろしく頼む」
そう微笑み返したフワワもまた、友達という不思議な響きに心がもぞもぞとするような感じはあったが、大きな口で笑いながら猫の手を卒業した、小さな手を引いて握手をした。
「うえ!!!」
「なんだ」
エンキドゥは握手した手こそ固く握りながらも、腕の長さの許す限り目いっぱい距離を取り、明後日の方向を向いた。両手を握られているから、フワワの酷い口臭鼻をつまむこともできず、応急処置として息を止めた。
「あなた、歯、磨いてる…?」
またしても気を失いそうになるのを踏ん張りながら、できるだけ口を小さく動かして空気を取り込まないようにしながらそう伝える。それを聞いたフワワがははは、と笑うのに、同じく笑顔を返したいが、到底かなわず、顔を歪め死にそうな顔をするエンキドゥだった。
この森についてはフワワの方がずっと知識があり、おそらく年齢的にもずっと年上であったが、教えねばならぬことは、教えねばならぬ!と奮起したエンキドゥはフワワに歯の手入れや服の洗濯の仕方を教えた。とはいえ、自分自身もここでの生活での歯の手入れは、体に染みついていた「それ用の道具」がなかったので、やわらかい木の枝を削りほぐして使ったりなどと試行錯誤の末に編み出したものだったが、それとて何もしないよりは500倍マシなのである。そうしてエンキドゥとフワワは、泉で一緒に過ごすことが多くなった。
フワワもまたここでの生活の知恵を惜しみなく少女と共有した。一番エンキドゥにとって魅力的だったのは「火」だった。40センチくらいの杉の森の丸太を3本持ってきたフワワは、地面に少し穴を掘り、その丸太を立てた。大きめの石で足元を支え、倒れないように丸太同士を寄りかからせる。
どうやったのか、目にもとまらぬ速さで火を起こし、丸太同士の間にできた三角の隙間に、木くずを入れ種火を放り投げる。丸太は乾燥していたので、火が移ると途端によく燃えた。ぱち、と火の粉の爆ぜる音を楽しみながら、夕暮れの底冷えの時間に暖を取りながら、魚を焼いて食べた。
「生で食べておなかを壊したよ」
と、ある日の一幕を振り返り、くすくすと笑った。そういった失敗を除けば植物類しか口にしていなかったエンキドゥにとって、この日の食事は格別だった。
そうしてエンキドゥは、フワワから火の起こし方や、土鍋、かまど、トーチ、囲炉裏などの作り方を学んだ。
「火は文明の起こりだ、ってね」
「ほう、頭のよさそうなことも、言うのだな」
エンキドゥは一発フワワの肩口にパンチを入れた。
フワワは、そうやって度々エンキドゥのところを訪れては、麦酒を飲みながら会話を楽しんだ。早速習得した火を通した簡単な料理でもてなすと、手に入らないような布や皮などの差し入れを持ってくることもあり、これは大いに助かった。
エンキドゥの快適平原ライフ…と思っていた、サバイバル生活のレベルは、短期間の間に驚異的なスピードで向上していった。黒ニンニクや各種燻製の作り方も学び、保存食や調理、それらに必要な器具などが全て次々と手作りされた。
かつて食べれる野草以外が奇妙にもおあつらえ向きに薙ぎ払われていた平原も今はそんなこともない。エンキドゥ自身が見分けがつくことになったし、わからなければフワワが来るまで口をつけず、教えてもらえばよいのだから。
「仕事がひとつ、減ったな」
「影」はそう一息ついて、ようやく人間らしい生活に近づいた少女の眠る顔を静かに見下ろした。