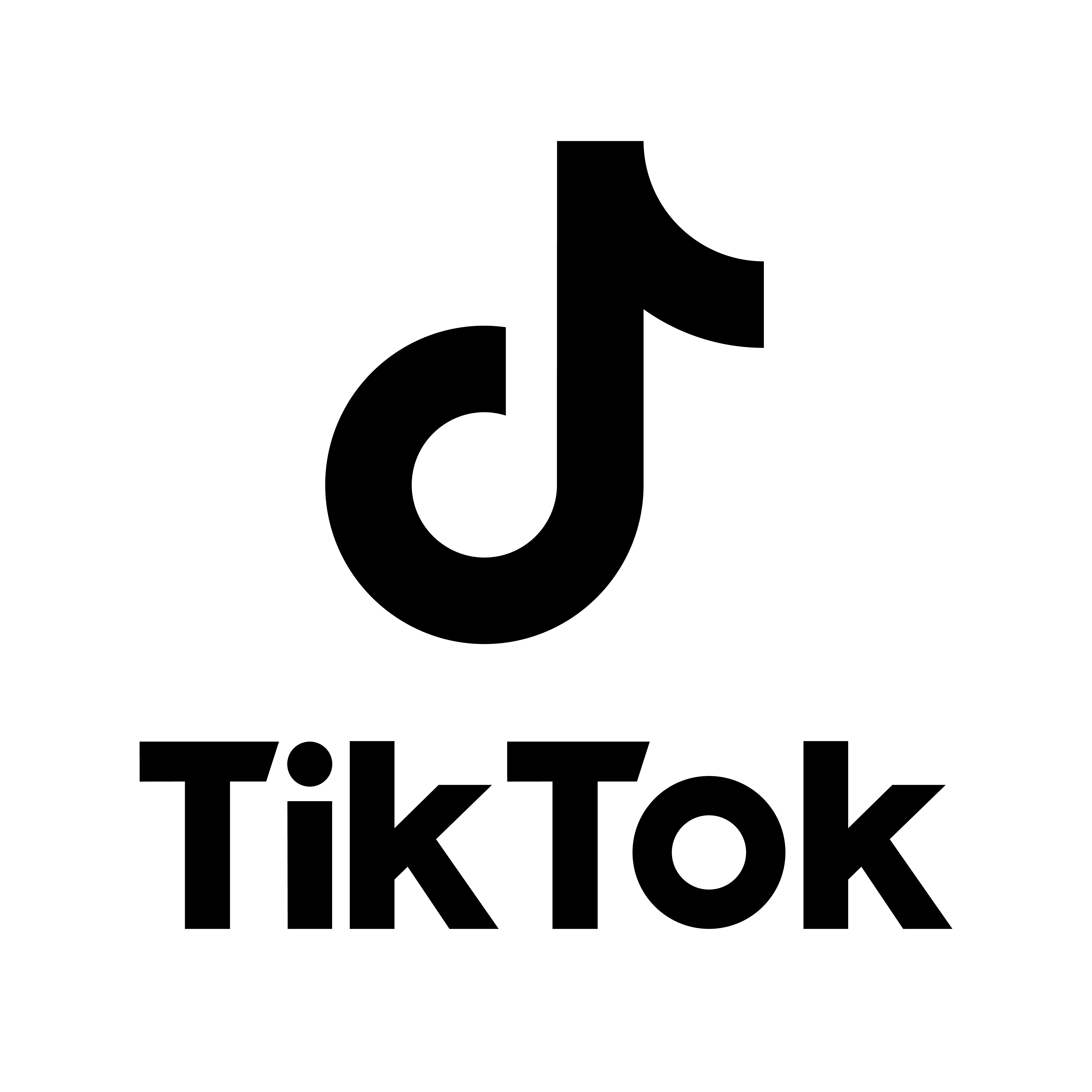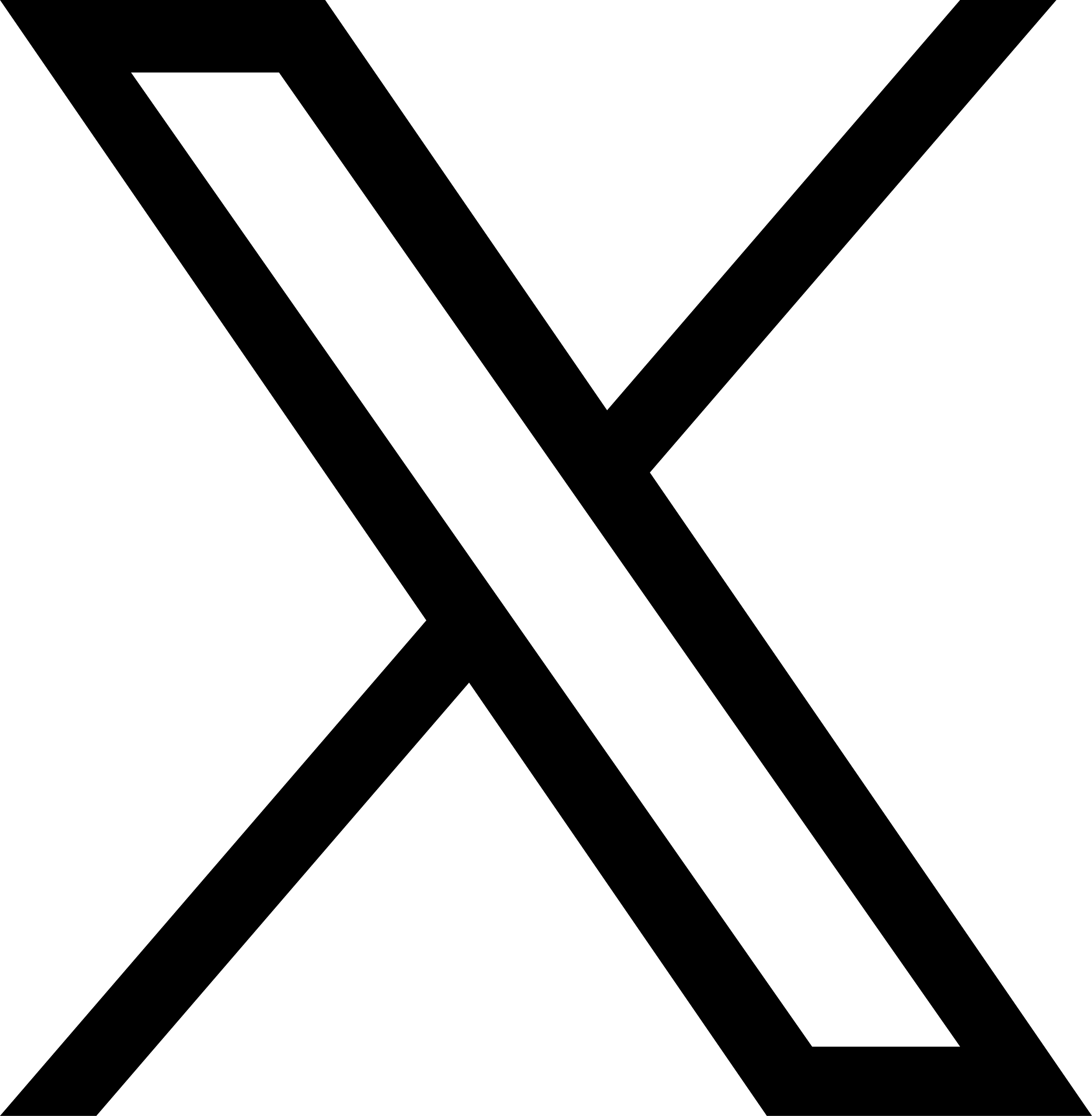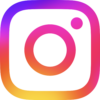第6節 ムシャハトの誘惑
その頃、ウルクの王ギルガメッシュは、執務室で部下であるウタナからとある報告を受けていた。それは森に生きる狩人たちから陳情があった、というものだった。詳しく聞くと、どうやら最近ウルクから離れた森の近くで、彼らが狩りをしていると、どこからともなく狂人のような野人が現れ、獲物を逃がされたり、罠を壊されたりということがあるようだ。場合によっては狩人自身が襲われるケースも出ているようで、いよいよ討伐を要請したい、というのが陳情の内容だ。
「それは、例のアヌが我に差し向けようとしている人間か?」
重々しく語るウタナに対し、ギルガッメシュは何かおかしいことでもあったのだろうか、にやりと口角を上げてそう答えた。
「アヌ様が?」
「いや、何。私の耳に届かぬ音はない」
何事か知っているのであろうギルガメッシュの茫漠とした話しぶりにウタナは首を傾げたが、そもそもギルガメッシュ王の言葉の意味するところを正しく捉えらぬことなど気にし始めてはきりがない、とウタナはこっそりとため息をついた。偉大なる神の名が出てきていたことは気に掛けるべき点ではあったが、今は目の前の王に詳しく話せと所望された、その命令の方が優先される、と判断して再び口を開いた。
「報告によると、そやつは杉森近くの原野付近に出現することが多いようです。野生の動物と肩を並べて水を飲み、草や木の実を食べ、自分自身もまるで野生の動物のような生活をしている、とも。ただ、野人、と評するものもあれば…」
「あれば?なんだ。続けろ」
「いえ、その、見た目は猫科の獣の姿の半獣半人ではあるが、実体はきわめて華奢な少女だと…そういった証言をしているものもおります」
「ほう。それで。」
「恐怖におびえれば人は小さなネズミの影を悪魔にも獅子にも錯覚するもの。さらば実像が小さかったとしても、その証言にも違和感はございますまい、と」
報告を終えたことを告げるように、ウタナが深く頭を垂れた。
ギルガメッシュは、椅子に肘をつき、指で顎をなぞりながら、しばらく床を眺めた。それから、おもむろに立ち上がると、そば仕えをしていたウタナの方を振り返り、いやらしいほどに人好きのする笑顔でこう答えた。
「ならば、神アヌが我に遣わした猫の獣人の使者、歓迎せねばなるまいな」
神を侮ってはいけません、と、ウタナは喉元までせりあがった小言をぐっと飲みこんだ。その溜飲が下がりきるのも待たず、ギルガメッシュは杞憂だと言わんばかりに、どこに問題がある?とでも言いたげな、おどけた表情を作って見せた。このふたりの付き合いは存外長いのである。
◆
数日後の夜半、ギルガメッシュはウタナを連れて、神殿男娼『ムシャハト』のもとを訪れた。
『ムシャハト』は神殿男娼グループの名前でもあり、そして彼らを率いるリーダーの名前でもあった。男娼、と名はついており、またその働きにも相違はなかったが、彼らはあまたの占術を使いこなす、神々の相談役でもあった。まさしく神の眷属であり、神殿男娼グループの中でもリーダー・ムシャハトは、特に神々からの信頼が厚かった。
ムシャハトの屋敷はウルクの神殿の中にあるものの、その他の区画とは明らかに異様な佇まいで、妖艶な雰囲気の漂う空間には慣れぬものが嗅げば酩酊してしまいそうなほどに香が焚きしめられていた。
ウタナはここには初めて訪れる。どこか落ち着かず、かといってあちらこちらに目くばせするのも憚られ、前を歩くギルガメッシュの背を追うことだけに集中するように気を向けた。
屋敷の回廊を門番に案内され、ギルガメッシュとウタナは、ムシャハトのいる居間に通された。靴で踏むのが憚られるような織物の絨毯、室内の明かりは薄暗いが視界を奪うほどではかった。主人であるムシャハトの席に人はおらず、ムシャハト本人はその座の隣に控えていた。
「ようこそお越し下さいました」
深々と例をしたムシャハトは、ウタナが思い描いていた男娼のイメージよりは幾分俗世じみて感じたが、それが王であるギルガメッシュを迎えるがゆえの当然の緊張であることを、王に慣れすぎたウタナは気づくことはなかった。
「久しぶりだな、ムシャハト。たいそう、景気が良さそうじゃないか」
「畏れ多くも」
腰を折るように優雅に礼をしたムシャハトのペースは気にかけることはず、王はここはいつもいい男が揃っているって噂だぞ、と、くつくつと笑った。それにムシャハトが礼を返す。ここまではひとしきりの社交辞令であることを双方理解しての、茶番のようなやりとりである。
ランタンのようなあかあかとした光を挟んで、しばし二人が視線を合わせたまま会話を止めた。ウタナとムシャハトの側近たちは、その空気の静謐にぴりりと背を震わせた。
「今日は少し相談があってな。…まあ、そうかしこまらずに、先ずは話を聞いてほしい」
こく、とムシャハトがうなずいて、それからもう一つの奥の間に、側近は下がらせ、客人二人だけを通す。ここからが本題なのだ。
応接用のソファにはギルガメッシュとムシャハトのみが腰かけ、ウタナはその後ろに控えた。王が視線をそらさずにじっと自分の方を見てくるから、ムシャハトはつきたかったため息をこっそりと飲み込んだ。2人は、もともと見知った仲なのだが、ムシャハトはギルガメッシュの奔放な性格が苦手であった。もうかなり昔のことであるが、娼館のメンバーを突然貸し切って飲み明かすことも度々あり、目についたものを近くに招いては異国の舞を所望したり、引き抜きまがいの甘言を吐いたりと、好き勝手サービスを求めるなど、典型的な「迷惑な」客だったのだ。しかし立場上無碍にすることはできず、かといって度し難く、さらに厄介なのが、それだけ迷惑をかけられてはいても心底憎むことのできない「求心力」を持っていることだった。
さて、本題だが、ともう一度ギルガメッシュが今度は真剣な顔で仕切りなおす。
ムシャハトは、唾をのむ音が静かな空間に響く錯覚さえあった。
とつとつと、依頼は小声で語られた。この館全体、どうしてか壁が薄いことを王はただしく理解していた。
「…ということだ。だからくれぐれも、内密に頼む」
また、にこり!と、わざとらしいほどの笑みに表情を戻したギルガメッシュに、ムシャハトはしばし言葉を失った。今聞いた内容の、その事実を精緻に思い返す。『これ』は、どう考えても…
「この仕事は、神アヌの怒りに触れるのでは?」
「何を、これは使者に対する、歓迎の印だ。おまえたちにこそふさわしい」
首をかしげ、すい、とムシャハトの目に焦点を定めるように指をさす。視線と指先、そして言葉という武器は自分たちのものだといっても過言ではないが、それを同じように巧みにあやつられている事実に、ムシャハトは理解しながらも苦い思いを消すことができなかった。
一方、王はウタナに目くばせをする。ウタナはそれを待っていたのか、すぐさま懐から布袋を取り出し、袋の紐をほどき中身が見えるようにテーブルに置いた。シャリ、という金属の擦れる音と、重みを感じる見た目の通り、その中には、金や宝石類の装飾品が入っていた。ひと際精緻に飾られていたラピスラズリは、今や金よりも高価とされている宝石の一つである。
滅多に目にすることもないその輝きに、ムシャハトは思わず感嘆の声を感じたままに漏らしてしまって、それから、生唾を飲み込んだ。
「着手金だ。成功すればこの5倍は出そう」
「…これだけでも十分です」
「王に二言はない」
ギルガメッシュはそれだけ最後に言い、ムシャハトの判断を待った。交渉事は、結果が明らかなところまで来てしまえば、あとは沈黙に勝る効力は何ものも持たないことをよく心得ていた。
しばしの間ののち、ムシャハトは腰かけていたソファからそのままそっと絨毯に片膝をつき、自分の黒曜の首飾りを見下ろすようにゆっくりと頭を下げた。
「お任せください。最高のもてなしで、任務を果たします」
神の契約は誓約となる。ウタナだけが、納得の行かぬ表情を浮かべていた。